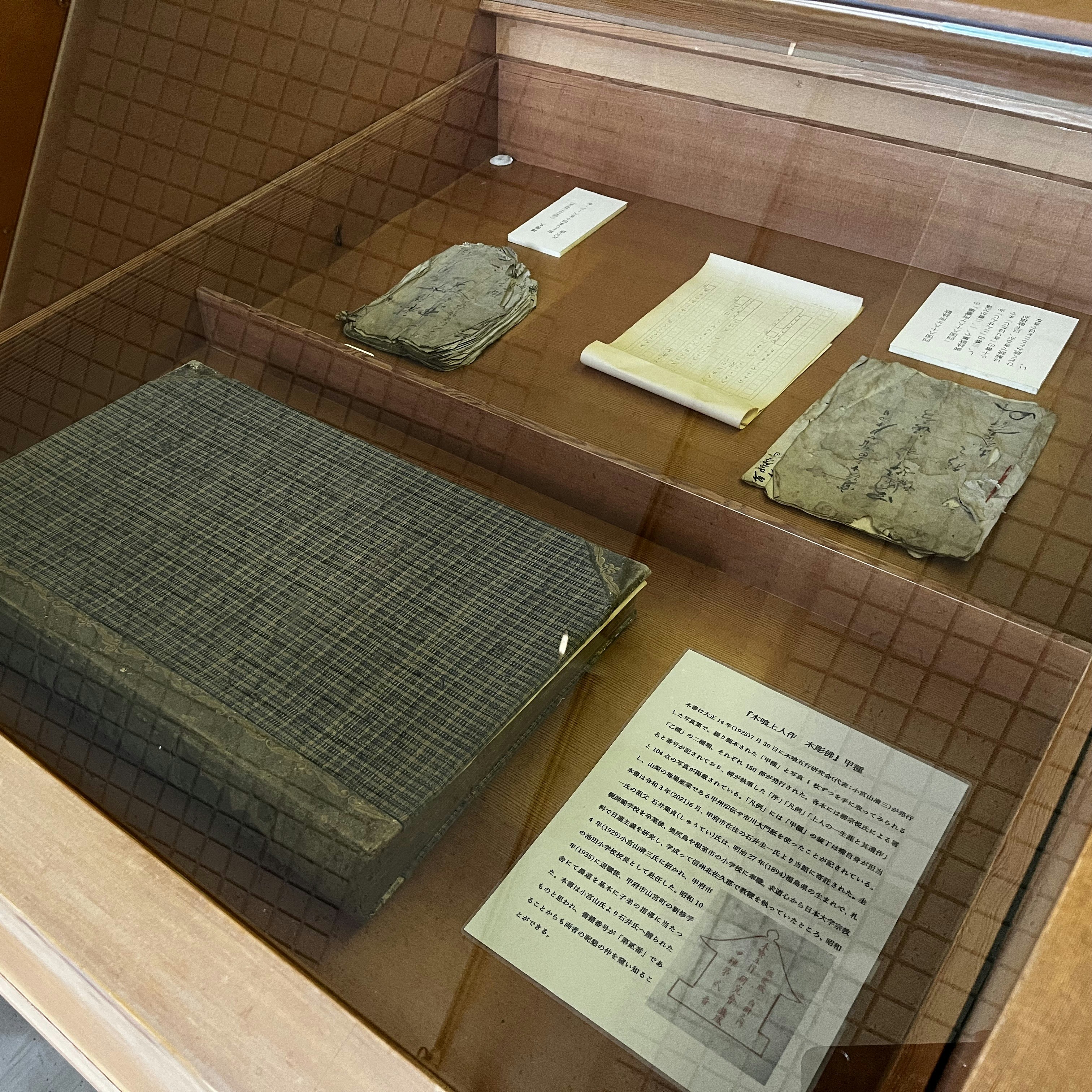「DESIGN MUSEUM JAPAN」がツアーを開催。第1弾は「深澤直人とめぐる山梨デザインの旅」
日本各地に存在する優れた「デザインの宝」を発掘し、クリエイターの視点でひも解くことでその魅力を可視化する「DESIGN MUSEUM JAPAN」。その初のツアー企画が開催された。記念すべき第1弾となった「深澤直人とめぐる山梨デザインの旅」の様子をレポートする。

日本各地に存在する優れた「デザインの宝物」を発掘し、クリエイターの視点でひも解くことでその魅力を可視化する「DESIGN MUSEUM JAPAN」。その初のツアー企画が開催された。
同プロジェクトは、日本に「国立デザインミュージアム」をつくることを目指す一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMによるもの。いままでNHKによる特集番組の放送や、国立新美術館では3度にわたってその成果が展覧会としてお披露目されてきた。今年の3月には、全国のミュージアムや研究施設と連携し、地域ごとのデザインアーカイヴをウェブサイトで一元的に集約・公開することを目指す「JAPAN Design Resource Database(DESIGN デザイン design)」もローンチされている。
特番や展覧会では、デザイナーやアーティストなど様々なクリエイターらが自身の目線で選んだ、その土地の「デザインの宝物」が紹介されてきた。今回初めて実施されたツアー企画は、その道程を参加者とともに辿るものとなっている。記念すべき第1回を務めたのは、プロダクトデザイナー・深澤直人による「深澤直人とめぐる山梨デザインの旅」だ。その様子をレポートしたい。