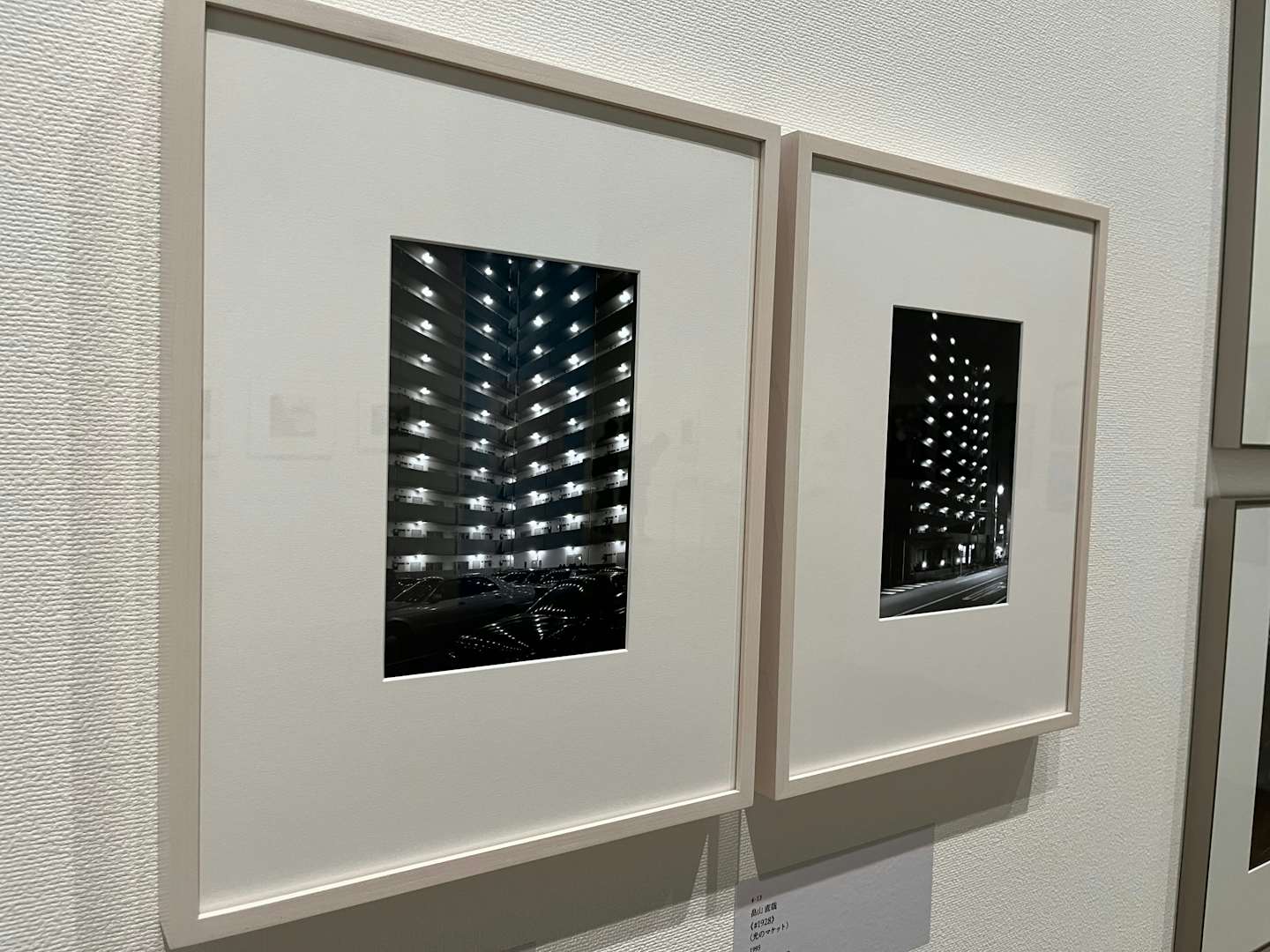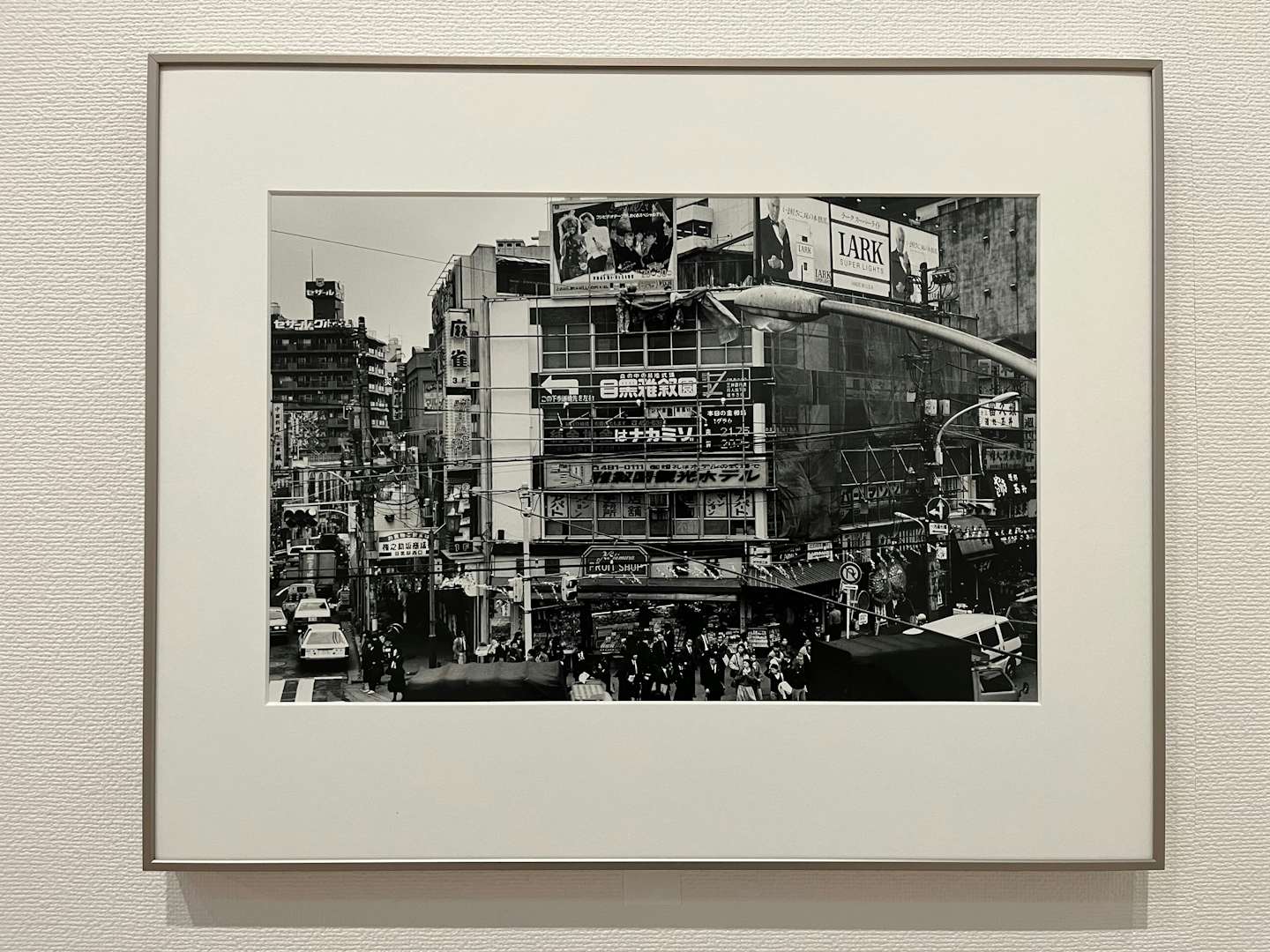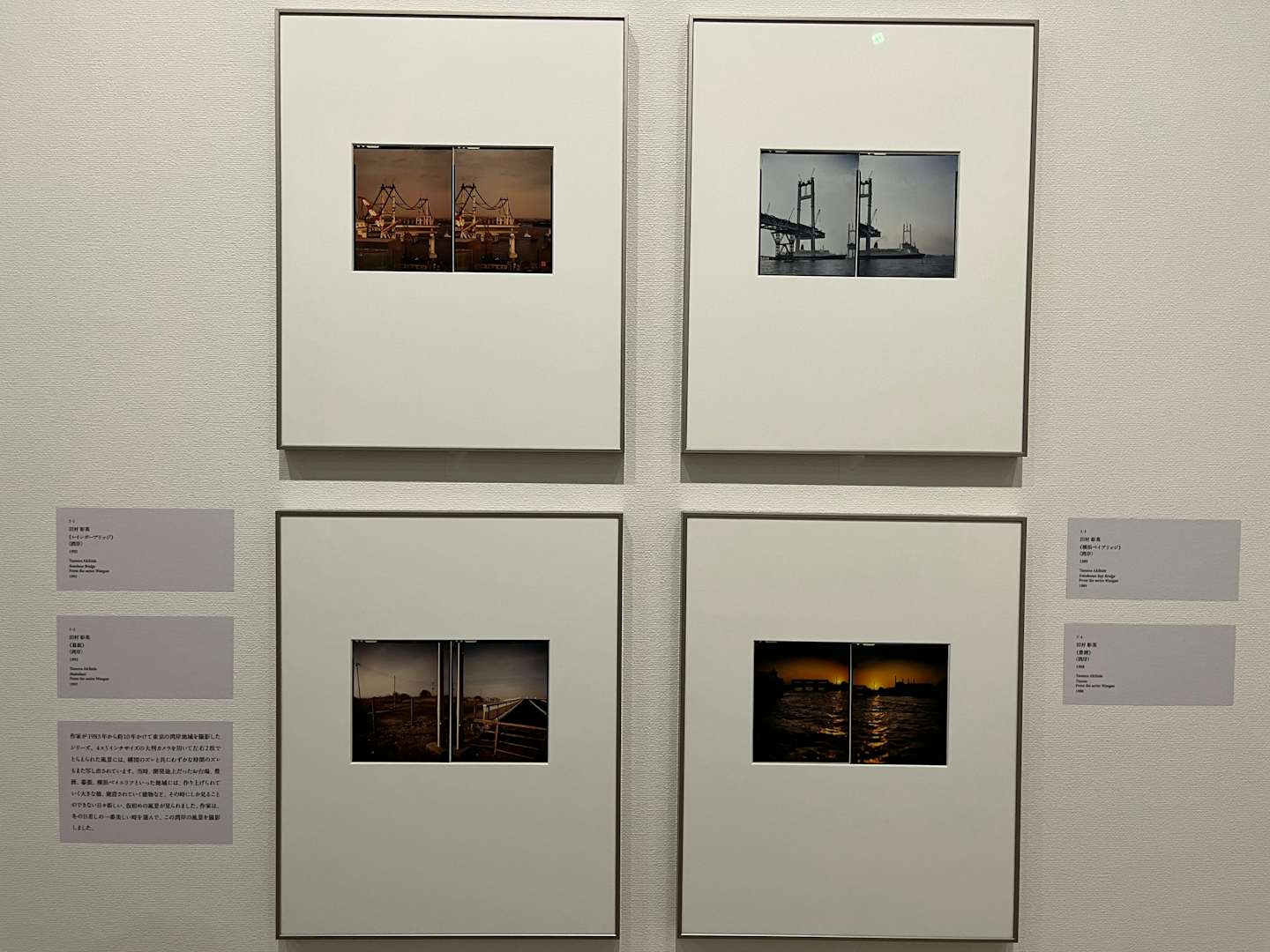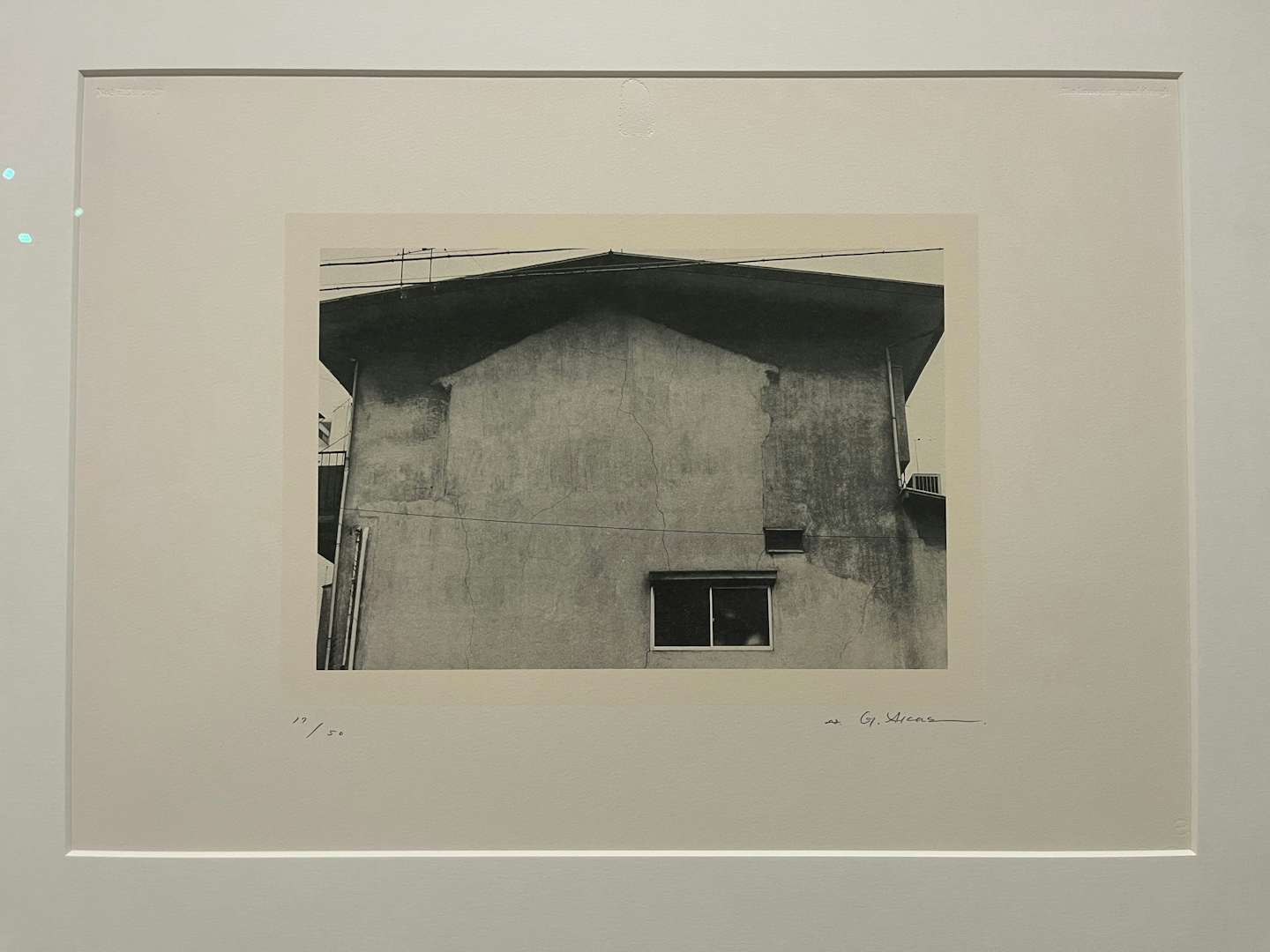「総合開館30周年記念 TOPコレクション 不易流行」(東京都写真美術館)開幕レポート。コレクションから改めて学ぶ写真表現史
東京都写真美術館で同館コレクションを5人の学芸員の視点から紹介する「総合開館30周年記念 TOPコレクション 不易流行」が開幕した。会期は6月22日まで。

東京都写真美術館で、2期にわたって7名の学芸員が10のテーマで構成するオムニバス形式の展覧会「総合開館30周年記念 TOPコレクション」の第1期「不易流行」が開幕した。会期は6月22日まで。

「不易流行」は5室構成で、それぞれ同館学芸員の佐藤真実子、大﨑千野、室井萌々、山﨑香穂、石田哲朗が担当している。本展のタイトル「不易流行」は、江戸初期の俳人・松尾芭蕉(1644〜94)が俳句の心構えについて述べた「不易を知らざれば基立ち難く、流行知らざれば風新たにならず(現代語訳:変わらないものを知らなくては基本が成立せず、流行を知らなくては新しい風は起こらない)」という言葉に由来する。このタイトルの通り、本展は同館のコレクションを改めて振り返り、時代を象徴する名作をテーマごとに交えつつ、ゆるやかに写真史をたどることができる展覧会となっている。